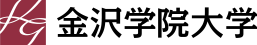お知らせ NEWS
珠洲市の奥能登塩田村で今年も「助っ人」に!
8月から学生たちが製塩作業 約40日間に渡り交代で現地入り
今年も珠洲市の奥能登塩田村で本学の学生たちが活躍します。能登に根付き、脈々と受け継がれてきた国重要無形民俗文化財「能登の揚浜式製塩の技術」による製塩作業を手伝うための説明会が7月14日、本学講堂で行われ、学生たちは真剣な表情で炎天下での作業に対する注意事項などに耳を傾けました。
説明会には奥能登塩田村の石田尚史社長と道の駅すず塩田村の神谷健司駅長、参加を検討する学生33人が出席。石田社長と神谷駅長は海水を桶で汲んで浜に運ぶ潮汲み、円錐形の打桶(おちょけ)で海水を砂にまく潮撒き、火加減が重要な荒焚きと本焚きなど揚浜式の製塩作業のほか、能登の里山の薪だけを使って塩をたき上げて里山と海の好循環を作り出していることやうまみの強い能登の塩について説明しました。
石田社長は「地震と豪雨からの復旧途上でまだまだ不自由な生活が続いているが、日本に唯一残る能登の揚浜式製塩を次世代につないでいくために皆さんの力を貸してほしい」、神谷駅長は「500年前と変わらない製法のため、炎天下での過酷な作業になるが、協力をお願いしたい」と期待を寄せました。
珠洲市での製塩作業は地震と豪雨による住民の長期避難などで深刻な人手不足に陥っており、昨年から本学の学生が「助っ人」として作業に参加しています。昨年は、学生が手伝った期間の収量が例年同時期の1・5倍になったほか、清鐘祭で能登の塩を使ったおにぎりとゆでじゃがいもをふるまい、能登の塩のPRにも一役買いました。
2年連続で製塩作業に参加するスポーツ科学部スポーツ科学科4年の入川康陽さん(埼玉・浦和実業学園高校出身)と経済学部経済学科4年の小谷日向汰さん(石川・鵬学園高校出身)は「旅行感覚で行くと挫折してしまうので、気を引き締めて作業をやり遂げたい」と話しています。
学生たちは8月から約40日間に渡り交代で珠洲市に入り、浜で砂をかき集める「浜取り」作業などを手伝う予定になっています。

能登の塩のおいしさや海と里山のつながりについて説明する道の駅すず塩田村の神谷駅長=講堂