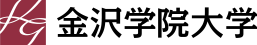お知らせ NEWS
力強い学生助っ人登場「今年も頑張ります!」
奥能登塩田村で製塩作業がスタート

炎天下の塩田で砂をかき集める「浜取り」など
 本学の学生有志による奥能登塩田村(珠洲市)の製塩作業が8月2日から始まりました。学生たちは、珠洲市清水町の道の駅すず塩田村内と馬緤(まつなぎ)町に設けられた計8枚の塩田で、砂をかき集める「浜取り」作業に連日取り組んでいます。
珠洲市の揚浜式製塩は砂にしみ込ませた海水を天日で乾かして使うことから夏の日差しが何より重要で、学生たちは酷暑の直射日光の下、柄振(いぶり)と呼ばれる道具で砂をかき集める作業に奮闘しています。本学学生有志は昨年から、地震による住民の長期避難等により深刻な人材不足に陥っていた奥能登塩田村の製塩作業に助っ人として協力しています。
本学の学生有志による奥能登塩田村(珠洲市)の製塩作業が8月2日から始まりました。学生たちは、珠洲市清水町の道の駅すず塩田村内と馬緤(まつなぎ)町に設けられた計8枚の塩田で、砂をかき集める「浜取り」作業に連日取り組んでいます。
珠洲市の揚浜式製塩は砂にしみ込ませた海水を天日で乾かして使うことから夏の日差しが何より重要で、学生たちは酷暑の直射日光の下、柄振(いぶり)と呼ばれる道具で砂をかき集める作業に奮闘しています。本学学生有志は昨年から、地震による住民の長期避難等により深刻な人材不足に陥っていた奥能登塩田村の製塩作業に助っ人として協力しています。
取材した8月4日の珠洲市の気温は37.5度。この日は40.3度を記録した小松市が日本で一番暑い地点になるなど、石川県は酷暑に見舞われました。日差しをさえぎるものが無い塩田の暑さは尋常ではなく、そんな環境で行う力仕事は過酷を極めますが、学生9人は柄振を引っ張り、砂を塩田中央に集め、垂舟(たれふね)と呼ばれる木製の箱に砂を入れていく作業を黙々と進めました。
グラウンド整備に使うトンボに似た「柄振(いぶり)」で、塩田の砂をかき集めます。学生たちが集めている砂は海水をまいて8時間ほど天日で乾かした「カン砂」。塩の結晶がたっぷり付いています。
「能登復興に貢献したい」
-スポーツ科学部4年 入川さん
「昨年参加し、今年も行くと決めていた」
ー経済学部3年 中嶋さん
「地元の雪かきと似ている」
ー文学部2年 悴田さん
 作業に当たっているスポーツ科学部スポーツ科学科4年の入川康陽さん(埼玉・浦和実業学園高校出身)は「昨年に続いて2度目の参加なので身体が覚えていた。自分ができることで能登の復興に貢献したい」と作業に取り組み、経済学部経済学科3年の中嶋康貴さん(石川県立金沢泉丘高校通信制出身)は「昨年の作業に参加し、震災被害を目の当たりにして、今年も作業に行くと決めていた。2週間しっかり頑張りたい」と汗でビショビショになったTシャツを絞りながら答えてくれました。
作業に当たっているスポーツ科学部スポーツ科学科4年の入川康陽さん(埼玉・浦和実業学園高校出身)は「昨年に続いて2度目の参加なので身体が覚えていた。自分ができることで能登の復興に貢献したい」と作業に取り組み、経済学部経済学科3年の中嶋康貴さん(石川県立金沢泉丘高校通信制出身)は「昨年の作業に参加し、震災被害を目の当たりにして、今年も作業に行くと決めていた。2週間しっかり頑張りたい」と汗でビショビショになったTシャツを絞りながら答えてくれました。
初めて作業に参加した文学部文学科歴史学・考古学専攻の悴田陸句さん(長野県大町岳陽高校出身)は「塩田作業は地元長野の雪かきに似たところがあり、楽しくやっています」と炎天下での作業にも笑顔で話してくれました。道の駅すず塩田村の神谷健司駅長は「炎天下での重労働はつらいものだが、金沢学院大学の学生さんは明るく、元気に作業に励んでくれて本当にありがたい。立派な戦力になってくれて頼もしい」と学生たちの働きに目を細めました。

えぐれて露出する山肌が見える。地震と豪雨の爪痕。
9月中旬まで約40日間
学生が交代で現地入り
学生による塩田作業は9月中旬まで約40日間行われ、その間21人の学生が交代で現地に入り、作業を行う予定です。
珠洲市の「揚浜式製塩作業の技術」は約500年にわたって脈々と受け継がれてきたもので、国重要無形民俗文化財に指定されています。日本で唯一、昔ながらの製塩技法がそのまま残る貴重な文化的遺産であり、珠洲市の大事な産業でもあります。珠洲の塩は塩味とうまみのバランスが良く、全国的に人気を集めています。